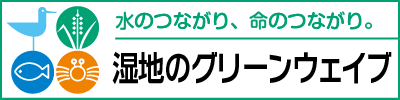有機栽培による水田農業と湿地保護・生物多様性保全の可能性
NPO法人民間稲作研究所 代表 稲葉光國
■湿地の一部としての水田農業の喪失
水田農業と湿地保護は違ったベクトルを持った存在である。水田は文字通りイネなどの食糧生産のエリアとして認識され、近代化とともに食糧の生産装置としての機能に特化してきた。大掛かりな土木工事ができなかったかつての水田は用排水がほぼフラットに形成され、水田は河川と一体化した水利環境であった。湿地とも連続し、水生動植物の移動も自由度が高かった。日本や韓国を除くアジア各国の水田は現在もそうした環境を残し、湿地の一部を構成している。
しかし、日本の水田は昭和40年代から2回にわたる大規模な基盤整備によって、用排水が完全に分離され、河川との連続性を失ってしまった。湿地の一部であった水田も盛土や暗渠排水によって乾田化がすすみ、イネを効率よく作るだけの装置となった。水路も3面張りのU字溝となり、生き物の住みかとしての機能を失った。土側溝が主流であった昭和30年代の土地改良までが、水田の生物多様性を失わない基盤整備であった。
他方、水田には昭和36年(1961年)から昭和46年(1971年)の10年間にわたって魚毒性の強い除草剤PCPが散布され、トキやコウノトリをはじめ貴重な動植物を死に追いやった。昭和48年から本格的に普及した稚苗田植機稲作は大量の農薬・化学肥料とセットになって普及が進み、併せて水田に水をあまり入れない管理やトンボの羽化前に水を切る栽培法が普及機関を通じて全国に普及した。
水田周辺の生き物が激減し、多様性を失ったのは言うまでもない。生産されるお米もミネラルが減少し、農薬が残留するという結果になり、その安全性や栄養的価値の低下が顕著になってきた。特に化学物質過敏症に悩む方々にはとても口にできないお米になった。
■水田の生物多様性回復の試み
多様性回復の試みは、稲作の分野と農業土木の分野からほぼ同時期に開始された。
稲作の分野では、農薬も化学肥料も使わない有機農業の模索であったが、当初から生物の多様性回復を念頭に置いていたわけではない。むしろ、食べ物としての安全性の確保であり、残留農薬解消の抜本的対策として農薬の使用を中止することであった。
減農薬運動として九州で始まった農薬削減運動は、宇根豊氏を中心に虫見板を開発し、スケジュール散布となっていた農薬散布を農家が自ら判断して使用するという主体性回復運動であった。同時に農薬使用の原因となった稚苗の田植機稲作を成苗に変え、病害虫の発生しない稲作技術の開発も小生などを中心に同時に開始され、昭和60年代には除草剤を除けば、農薬の使用は必要ないレベルまで実践的研究はすすんでいた。
最後に残った問題は除草剤をどう除くかという栽培法の確立であった。除草剤を使わない栽培法が多くの農家で実践されるようになってきた。なかでも、アイガモ農法、紙マルチ農法、深水管理法、米ぬか農法などが有力な方法として提案され、それぞれ任意の研究団体が設立され普及活動が行われてきた。そのなかで、水田生物の多様性を活かした抑草技術の確立が強く意識され、本格的な研究開発が行われるようになってきたのは平成11年の「除草剤を使わないイネづくり」(民間稲作研究所編、農文協刊)の出版からであった。
平成12年、東京で開催された第3回環境保全型稲作技術全国交流集会には冬期湛水による抑草技術が始めて紹介され、野生生物との共生という視点から抑草技術が検討され、その多様な展開の可能性が予見されるようになってきた。その後国内での交流会議は開催がなくなり、代わって日韓中環境創造型稲作技術国際会議に引き継がれ、東アジアの稲作技術の発展をめざした技術確立運動に引き継がれることとなった。宇都宮で開催された第8回日韓中環境創造型稲作技術国際会議は環境団体と稲作農家、消費者団体が一堂に会し、ラムサール条約水田決議への提言を共有する集会となった。その後この集会は中国長春、韓国ウルチンの集会を経て、今年7月2〜4日に兵庫県豊岡市で開催され、水田生物の多様性を育む農業の現場視察を始め、各地での取り組みが発表され、生物の多様性を育み、それを栽培に活かした農業が慣行栽培を超える実力を備えつつあることが確認された。
水田生物の多様性を活かした稲作は冬期湛水、早期湛水、2回代かき、ふゆみずたんぼ、はるみずたんぼ、冬草たんぼなど、多様な手法が提唱された。しかし言葉だけが一人歩きすると農業現場は雑草に覆われ、かなり悲惨な労働が強いられる場合が多い。また根ぐされなどによる収量の低下が恒常化し、生物の多様性を活かした有機栽培では収量の低下はやむを得ない事象として受け止められる傾向もでてきた。
農業土木の分野からは水谷正一氏を中心に水田魚道の設置などによる生き物のバリア解消手段が提案され、「NPO法人田んぼ」や「NPO法人生物多様性農業支援センター」などによる生き物調査や農地・水・環境向上対策事業などの施策展開もあって、幅広く普及するようになってきた。
■水田の生物多様性を育む農業─その現場のからの問題提起
2010年7月2日〜4日兵庫県豊岡市で開催された「第1回水田生物の多様性を育む農業国際会議」は、その成果を踏まえ、CBD-COP10への提言書を採択した。恐らく農業者を中心としたCBDへの提言はこれが唯一ではないかと思われる。
生物多様性条約第10回締約国会議への提言(案)
第1回生物の多様性を育む農業国際会議(ICEBA/1)からCBD/COP10へ
1. 水田を中心としたアジアの農業は生物多様性の宝庫であった。
中国長江流域を中心に何千年の長きに亘って水田農業が営まれ、多様な生き物と多くの人々を養ってきました。毎年、一定期間湛水される水田はドジョウやフナなどの淡水魚やイトミミズ・ユスリカ、タガメ・ヤゴといった水生昆虫、そしてカエルなどの両生類などさまざまな水辺の動植物を育んできました。そしてその数は日本だけでも5668種に及ぶことが農業者・研究者・市民の共同調査で明らかになりました。
2. 自然の循環機能を無視した近代農業が生物多様性を破壊した。
豊かな生き物の住みかであった水田が、その機能を失ったのは20世紀後半以降で、水田の長い歴史の中では極めて短い期間です。生物多様性の喪失はまず化学合成農薬の使用から始まりました。そして水田の基盤整備や、それに伴う河川や水路の大規模な改修工事によって決定的なダメージを受けました。日本国兵庫県豊岡市に最後まで生存したコウノトリはこうした近代農業の普及によってその最後の命を奪われ絶滅しました。
3. 生物の多様性を回復する農業者の挑戦
生物の多様性を育む農業国際会議に参集した東アジア各国の農業者は水田農業がふたたび多様な生き物の住みかとしての機能を回復するために化学農薬や化学肥料、遺伝子組み換え技術を使わずに、豊かな穀物の生産を可能にする技術の在り方を求め、10年間にわたって交流を進めてきました。さらに4年に及ぶ、市民による水田の生物多様性調査交流を進める中で、生物多様性を支えてきたのは、伝統的な農民の知恵であり、日常活動であることが明確になりました。これまでの経済的評価で測ることのできないこうした日常の生物多様性を向上させる行為を認識し、具体的に行動、評価する仕組みを政策に反映し、支援することを要請します。
私たちは、生物多様性に富んだ土地で健康な苗を、適切な生育空間を保ちながら育て、生きものの活性を高める生態系を維持することに熟練すれば、一定以上の生産性を持続可能に維持できる農業が可能であることを見出してきました。水田の湛水状態を長期に維持することや、時に畑として使用し、豊かな自然の循環機能や生態系の健全な復活に成功すれば、生産力を維持しながら地球資源の浪費を抑制し、CO2の大幅な削減が可能であることを確認してきました。
4. 生物の多様性を育む農業の啓発・普及を
生物の多様性を育む農業国際会議に参集したアジアの農業者は、その豊かな環境を維持増進し、それを活用するための農業のより一層の発展と普及のために尽力することを決議しました。私たち参加者一同は、生物の多様性の維持を願う世界各国の人々に、農業が環境破壊産業から環境を創造する産業に転換することが可能であることを確認し、持続可能な農業の完成に向けて努力することを提言いたします。
また、逼迫する食料危機に世界各国が食料基地を海外に求め、貴重な自然を破壊しながら、自国の食料を確保しようとしている潮流の先に、人類の未来はないことを認識し、各国がそれぞれの国の自然資源とその循環機能を活かした持続可能な農業の推進に向けて努力することを提言します。
2010年7月4日
第1回 生物の多様性を育む国際会議
(第11回 日韓中環境創造型稲作技術会議)
(第5回 日韓田んぼの生きもの調査交流会)
参加者 一同
特に3カ国から参加した農業者の提言という意味で、今日における環境に配慮した農業技術の世界的な到達点を示すものになったといえる。それだけに、その技術の実態と発展の方向や可能性について関係者の方々が認識を共有する必要があるように思われる。
集会に集約された稲作技術としての完成度はかなりハイレベルになってきたことが確認された。冬期湛水による稲作現場を2箇所見学する機会があったが苗質と冬期間の水管理によって成功と失敗が分かれ、極めて微妙な作業、特に一定の水位を保つ水管理が重要なファクターになることが浮き彫りになってきた。早期湛水も健苗を使い、緑肥や冬場の雑草を漉き込む手法や根ぐされを防止するために敢えて代かきをしない方法などと組み合わせて安定した抑草ができることも現場の視察と発表によって確認された。水田生物の多様性を育むという農法が多様な水田生物(動植物)によって支えられる実態が見えてきた。特に今問題になっている「ネオニコチノイド系農薬」(神経伝達阻害剤・みつばちの大量死・化学物質過敏症患者や若者への悪影響が問題になっている)によるカメムシ防除を行った減農薬栽培水田がカメムシの被害に会い、全く使用しない無農薬・有機栽培の水田で被害がなかったという報告は、全国的に確認されてきている事象であるが、豊岡の無農薬団地で確認された意義は非常に大きいものがあった。
しかし、提言書に書かれた「生物多様性に富んだ土地で健康な苗を、適切な生育空間を保ちながら育て、生きものの活性を高める生態系を維持することに熟練すれば、一定以上の生産性を持続可能に維持できる農業が可能であることを見出してきました。」という内容を実際の現場で実証し、その技術を普及するためにはまだまだ多くの継続的な努力が積み重ねられる必要のあることも事実である。それは水田も自然も多様性に富んでおり、Aで通用した技術がBでは全く通用しないことが多い。成功事例と失敗事例を蓄積しながら、そこに共通する事象を探り当て技術的安定性を確立する努力は今後も地道に継続しなければならない状況である。
また、今年度から提起されたイネ-麦―大豆の2年3作による有機栽培は、水田を一時的に畑として使用し、根粒菌を活用しながら麦やイネを育て、イネの雑草も抑制するという方法であり持続可能な低資源、低コストな農法であり、自給率の低下に歯止めがかからない日本や韓国に普及する必要がある。麦を刈り取った跡に水を張るとシギ・チドリが飛来するからそれを普及しようという環境保護団体からの提案は気持ちは理解できるが、安全な食料と豊かな環境の回復を願う有機農業者からみれば生産調整という愚策を認め、農業者の努力を逆なでする提案であることをご理解いただきたい。また、世界的な食糧危機が予想されるなかでアジア各国の稲作を現状のまま「湿地の賢明な利用」の典型として肯定し、紹介するのも現地の農家の意向に反しないかどうか慎重に判断する必要があるように思う。
環境保護に関心をよせるみなさまにとって、湿地のもつ役割を強調するのは当然ですが、そこを生活の糧としてきた農業者は多種多様な自然に囲まれ、常に変化する環境と向き合い、1年に1回しか体験できない多様な農業を営んでいる。農業技術の発展と普及には多くの歳月と経験の積み重ねが必要で、その進歩はゆったりと進まざるをえないこともご理解いただきたいと思います。
(ラムネットJニュースレターVol.4より転載)
2010年07月21日掲載